“ゆうゆうポイントシステム”内製化の成功要因とは?

2024年11月にサービスを開始した“ゆうゆうポイント”。日本郵政グループ初となる独自のポイントサービスは、企画構想から10か月というこれまでにないスピードで実現しています。 今回は、“ゆうゆうポイントシステム”内製化プロジェクトの中核を担う3名に話を聞きました。
エンジニアリング部 シニアマネージャー
佐々木 聡
ポイントシステム開発チームリーダー。技術選定、アーキテクチャ設計など技術系全般を担当。また、“ゆうゆうポイントサイト”構築の責任者も務める。
エンジニアリング部 ジェネラルマネージャー
小山 一博
ポイントシステム開発責任者。ビジネスサイドの要求を踏まえたポイントシステム構築の方針策定、設計を担当。
グループDX企画部 ジェネラルマネージャー
森永 龍文
グループDXプロジェクトの全体PM。ビジネスサイドやエンジニアサイドの調整、“ゆうゆうポイント”も含むグループDX施策の開発マネジメント全般を担当。
企画構想から10か月! これまでにないスピードで実現した“ゆうゆうポイントシステム”
──“ゆうゆうポイントシステム”の内製化に至った経緯を教えてください。
森永 最初にポイントサービスの構想が話されたのは2024年の1月です。
元々、日本郵政グループのDX推進において様々な開発を内製化していくことは基本方針でした。
それまでもサブシステムレベルでの内製化の実績はありましたが、“ゆうゆうポイントシステム”は、システム全体を内製で開発を行った初めての事例です。
これまで当社のシステムの多くは外部ベンダーに開発を委託してきましたが、今後もそれを続けていくと、どこかで限界が来てしまうし、改善のスピードも落ちてしまいますよね。
特にお客さま目線でクイックに改善しなければならない部分は、内部で対応できた方がいいと考えたんです。
また、多くの企業で内製化がDXの大きな成功要因になっていることも後押しになったと思います。
佐々木 開発のスピードが速いこと、柔軟な対応ができることが内製化のメリットでしたね。
小山 そうですね。“ゆうゆうポイント”は郵便局からスタートしましたけど、日本郵政グループ各社のサービスとの連携も見据えた設計にできました。
森永 日本郵政グループの特性や、今後システム上どんな要求が発生するか考えながら開発しなくてはならないので、エンジニアリングのメンバーたちは苦労されたんじゃないかな。
佐々木 大変ではあったけど、内製化することでゼロからカスタマイズできるという部分は良かったと思います。 苦労した分、面白さはありましたね。

成功のカギはチームビルディング! 外部ベンダーとのパートナーシップの重要性
── プロジェクトを推進する中で工夫したことを教えてください。
小山 ポイントシステムはJPデジタルが内製化しましたが、“郵便局アプリ” との機能実装や、ポイントシステムのエンジン部分については、必要に応じパートナー企業とも連携した体制で挑みました。
進めていく中で、各社とのコミュニケーションを密に取ることはかなり意識しましたね。パートナー企業が持つ機能の本質も質問する前に徹底的に調べて、同じ目線で会話できるようにしていました。
あとは、各社の責任分界点をシステム的に明確にしていました。
「これ、どちらのパートナー企業が開発するんだっけ?」という事態が起こらないよう意図的に分断したんです。
パートナー企業同士が直接コミュニケーションを取る機会も基本的には作らず、必ずJPデジタルが真ん中に立って進行する体制を組みました。
森永 それも成功要因の一つですよね。 各社の役割分担が明確だから、開発が滞ったときも原因特定が比較的容易でPMとしては有難かったです。意図的だったのかぁ・・・。 さすが。
佐々木 JPデジタル側の体制としては、ポイントシステムの開発に合わせてメンバーが急増したので、メンバー間のスキル差を埋めて開発チーム全体のスキルを向上させることに取り組みました。
最初は必ず手練れのエンジニアと新メンバーがツーマンセルで動くように工程を振り分け、組み合わせも機能ごとに切り替えていったんです。いろんな方とペアで動いてもらうことでスキル向上にもつながりますし、チーム内のコミュニケーションも取りやすくなります。
チームの仲が良い状態って実は大きな成功要因になるので、チームビルディングするうえで大事にしていました。
あとは、納期が近づいてくるとピリついてくることを前提に、メンバー間の不協和音を起こさないよう管理職としてはとても気を遣ったのは確かです(笑)
メンバーには、「急拡大したチームなので不安なのは自分だけじゃないから安心して」「常に相手を尊重して会話しよう」、そしてJPデジタルのモットーでもある「明るく、楽しく、元気よく、スマートに。」を繰り返し伝えていました。
小山 実はメンバーの採用には私のこだわりが一つあって。それは、スキルの高さだけを求めるのではなく、コミュニケーション力の高さも重視したことです。
自分の経験上、そういった人は指示された作業だけでなく主体的に考えて動いてくれたり、誰かが困っていたら助けたりする傾向があると。そういうところを期待しないと開発スクラムは回しにくいだろうなと考えてたから。
この採用方針はチャレンジでもあったんですけど、結果に結びついて本当に嬉しかったですね。
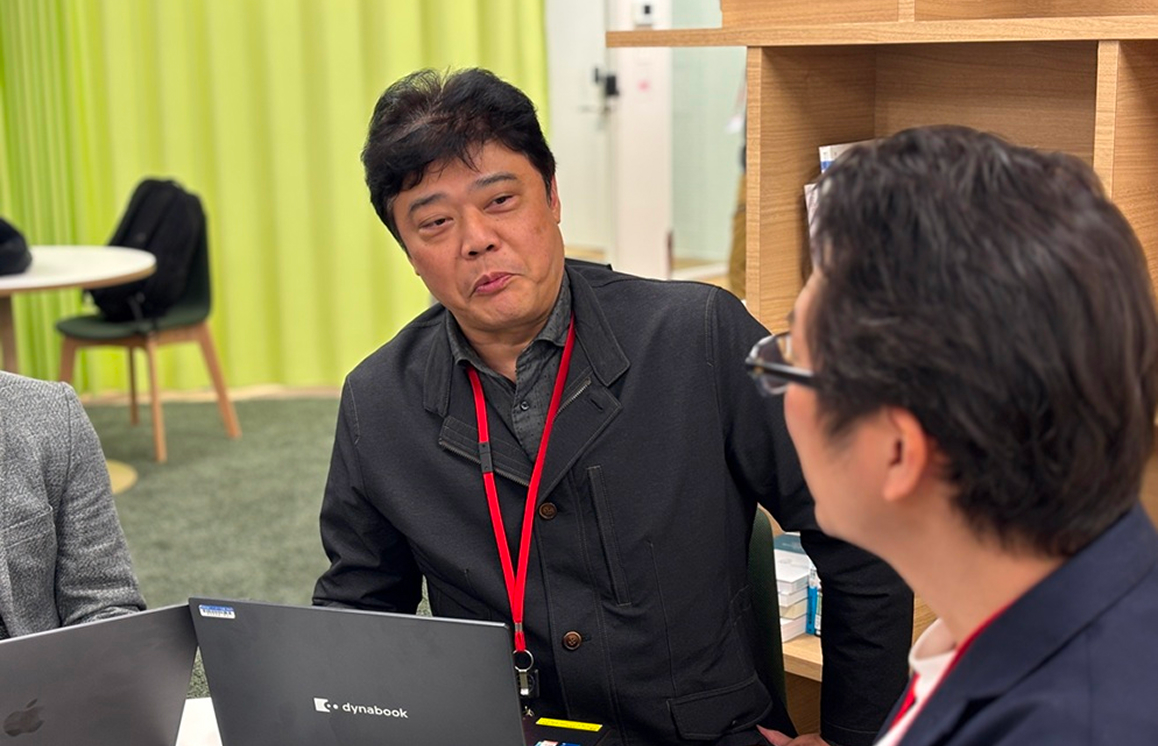
JPデジタルだから実現した、グループ連携を見据えたシステム設計
──「“ゆうゆうポイントシステム”のここがすごい!」と思うことを教えてください。
小山 最初からグループ会社まで意識して開発したことじゃないかな。
多くの企業では、まず自社のサービスに最適化したシステムを開発して、それをグループ会社が気に入ると導入するという流れが多いんです。
佐々木 たしかにそうかも。日本郵政グループ規模の会社で最初からグループ会社を意識した設計ってあんまり聞いたことないですね。
小山 日本郵政グループ全体を横断して支援するJPデジタルだからできたことかもしれないですね。
開発体制がスクラムになっているからサービスを運営するビジネスサイドと開発を行うエンジニアサイドに一体感があるし、施策に対してもクイックに対応できています。
森永 僕は、日本郵政グループの中でポイントサービスを活用できるシーンが多岐に渡るのは強みだと思います。
ポイントサービスを始めたものの、ポイントを貯める、使う機会をどうやって生み出すのか悩む企業って結構多いんですよね。
日本郵政グループだとお客さまがポイントを使える可能性がいろんなところにあって、悩まなくていいのはすごく恵まれていると思います。
それに伴って開発も必ず発生するので、エンジニアとしてはやりがいがあるんじゃないですか?
佐々木 こんなに大規模でありながら伸びしろも大きい事業ってなかなか無いですよ。軌道に乗るまでは必死ですけどね(笑)

不安を乗り越え、開発メンバーにとっても成長の機会に
──プロジェクトを進める中で印象的だった出来事を教えてください。
森永 やっぱりすべてが順風満帆とはいかず、途中で予期せぬトラブルが発生したこともありました。
そのとき全員で一致団結して対応したことは印象に残っていますね。
エンジニアリング部では小山さんが陣頭指揮を取って、状況を正しくドキュメントにしてトレースしたり、抜け漏れなく役割分担したり、負荷が高くなったら休ませるような配慮もしていた。エンジニアメンバーがその感覚を持っているのってすごいなって。
ネガティブに聞こえるエピソードかもしないけど、PMである僕にとっては、凄いなあって思った出来事です。
小山 サービスリリースの直前ってJPデジタルのメンバーもちょっとナーバスになる時期があったんです。開発が間に合うのか、大丈夫なのかって不安が集まってくるというか。
だけど、そこで誰一人として誰かを攻撃するような文句は出なかった。なんとかしようって前を向いてくれていた。それは頼もしかったし、印象的でしたね。
技術者には、一度こういう経験を積むとそれを糧にステップアップする瞬間があると思っていて。
今回のプロジェクトでは、その一歩を踏み出したメンバーが大勢いたことが最高だなと思っています。
“ゆうゆうポイントシステム”の先に目指すもの
──今後の展望を教えてください。
森永 これから強化していきたい点が二つ見えてきています。
一つは、ポイントサービス自体の強化。
日本郵政グループって非常に多くのお客さまにご利用いただいているので、“ゆうゆうポイント”は今まで以上にお客さまファーストなサービスになっていかなければと思います。マンパワー的な頑張りではなく仕組みとしてできる体制を整えていく必要があると考えています。
二つ目は、スクラム機能の標準化。
複数の企業が連携する複雑な開発プロジェクトが今後も円滑に進むようなルール作りや標準化を推し進めていきたいです。
佐々木 今回、チーム全体の雰囲気づくりや開発の環境といったチームビルディングが成功したと思っています。その経験を積んだメンバー達が様々なチームで活躍することで、チームの遺伝子を広げてくれたら嬉しいですね。
技術面でも内製化として一つ安定した事例を作れたので、どんどん横展開して他のプロジェクトでもクイックにシステム構築が出来ればといいなと思います。
小山 日本郵政グループ各社を見ていると、システム開発の面で私たちが貢献できることは山ほどあると思います。お客さまニーズや時代の潮流に合わせて、積極的かつスピーディーに実行できる私たちの強みを活かして、お客さまへ最新かつ最適なサービスをお届けできるよう郵政グループ全体を技術支援していきたいです。
関連する事例・取り組み
JOIN US!
一緒にみらいの郵便局をつくりませんか?
とても身近な郵便局が変わることは生活が変わるということ。
あなたの小さな気づきがお客さまの生活を変えることになるかもしれません。
そんな期待に胸を弾ませながら、楽しくチャレンジしていける仲間を求めています。


